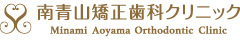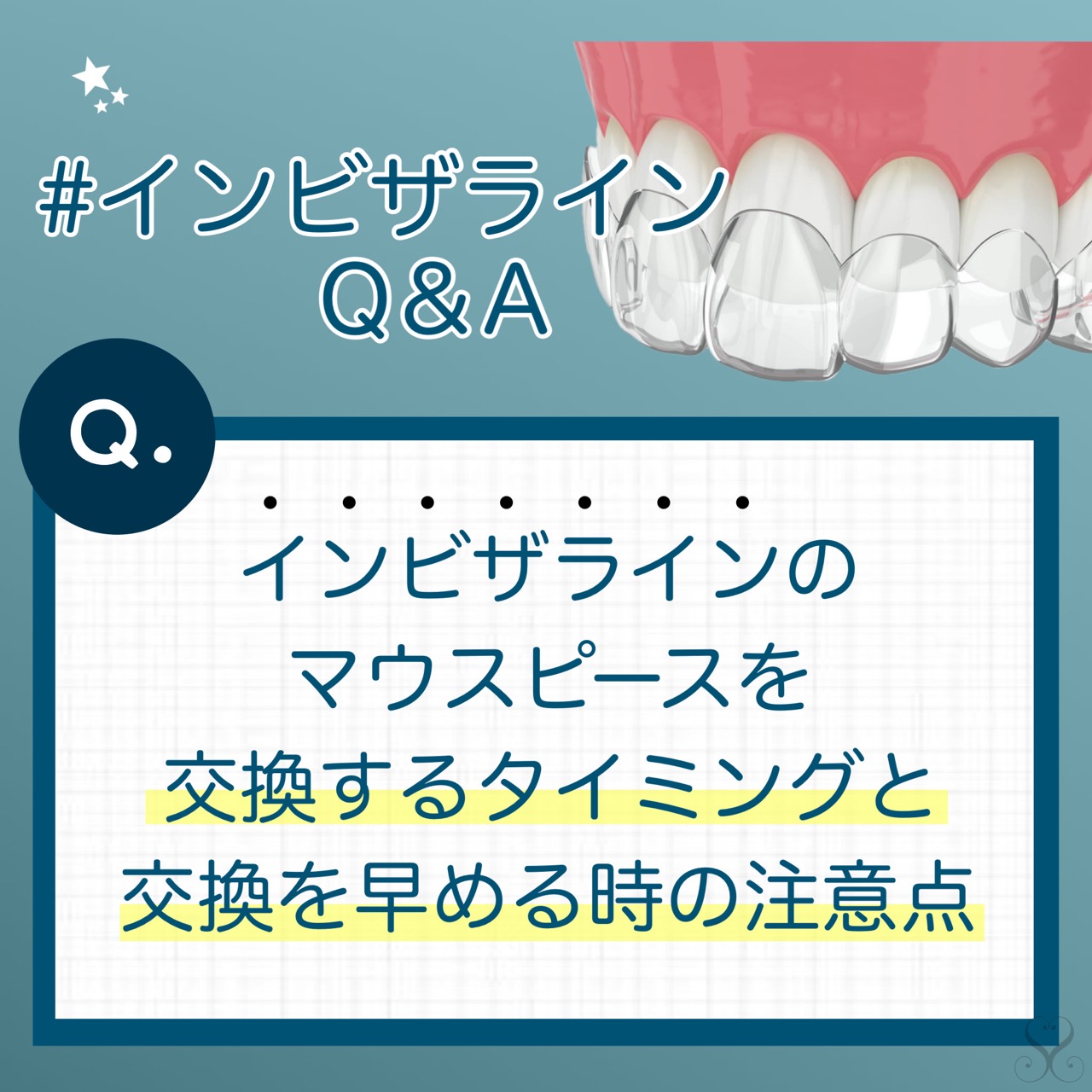歯並びは遺伝するの?歯並びを悪くする生活習慣や悪癖も解説

親子で顔が似ているように、親の歯並びと子供の歯並びを比較してみると、たいへん似ていることがあります。
それでは、歯並びは親から子へと遺伝するのでしょうか。歯並びに関係する要素は、遺伝だけなのでしょうか。
この記事では、歯並びの遺伝について解説します。
この記事を読むことで、歯並びと遺伝との関係、遺伝以外の歯並びに関係する要素などが理解でき、下記のような疑問や悩みが解決します。
こんな疑問を解消!
- 歯並びと遺伝の間に関係性はあるのか
- 歯並びに関係する遺伝性疾患は何か
- 歯並びに関係する遺伝性疾患以外に遺伝的要素はあるのか
- 歯並びは後天的影響を受けるのか
- 後天的影響を受ける場合、どのような原因があるのか
目次
歯並びと遺伝について
歯の形や大きさ、数、顎の骨格の形や大きさ、上下の顎の骨格の位置関係などは、歯並びに大きく関係しています。
これらは、遺伝との関係性が指摘されています。
遺伝性疾患
歯の形態、数、顎の形態、大きさなど、歯並びの構成要素と関係している遺伝性疾患は次のとおりです。
唇顎口蓋裂
唇顎口蓋裂は、上顎や上口唇に見られる先天異常です。
発生頻度は心臓奇形の次に多く、400〜500人に1人の割合で発現します。親が唇顎口蓋裂の場合、4〜5%ほどの確率で唇顎口蓋裂の子供が出生するという報告もあります。
唇顎口蓋裂では、上顎骨の成長が弱いため、上顎前歯の舌側傾斜による反対咬合になりやすいです。また、上顎の側切歯や第二小臼歯などに先天欠如が多く見られます。
なお、思春期以降、横顔が中顔面部が低い三日月様顔貌になる顎変形症にもなりやすい傾向があります。
骨形成不全症
骨形成不全症は、歯の形成不全を生じる先天的疾患です。
発生頻度は、2〜3万人に1人です。
骨形成不全症の歯は、エナメル質が剥離しやすいです。これにより、咬耗し、咬合高径が低下することで、歯列不正をきたしやすい傾向があります。
骨形成不全症の原因は、常染色体性の劣性遺伝です。
ピエール・ロバン症候群
ピエール・ロバン症候群は、小下顎症や口蓋裂の原因となる先天的疾患です。
発生頻度は、2,000〜30,000人に1人です。
胎児期における胎児の体位の影響が指摘されていますが、遺伝性という報告もあります。
トリーチャー・コリンズ症候群
トリーチャー・コリンズ症候群は、下顎骨の形成不全を生じる先天的疾患です。
発生頻度は、5万人に1人ほどです。
その原因は、常染色体の優性遺伝です。
外胚葉異形成症
外胚葉は、毛髪、爪、歯、汗腺などの元となる組織です。
外胚葉異形成症は、この外胚葉の形成に異常が生じる病気の総称です。
発生頻度は、5,000〜6,000人に1人ほどです。
外胚葉異形成症では、円錐歯という歯の形や大きさの異常、歯の先天的欠損などを生じやすいです。
外胚葉異形成症は、常染色体の劣性遺伝で遺伝します。
鎖骨頭蓋異形成症
鎖骨頭蓋異形成症は、過剰歯や埋伏歯、歯の萌出遅延などにより歯列不正の原因となる先天的疾患です。
発生頻度は、20万人に1人ほどとたいへん稀です。
鎖骨頭蓋異形成症は、常染色体の優性遺伝によって起こります。
先天性無歯症
先天性無歯症は、いずれかの歯が生まれつき欠損する病気です。
先天性無歯症は、常染色体性劣性遺伝で伝わります。
先天性多数歯欠損症
先天性多数歯欠損症は、生まれつき永久歯が6本以上欠損している病気で、部分性無歯症ともよばれます。
先天性多数歯欠損症は、常染色体性の優性遺伝です。
遺伝性疾患以外の遺伝的影響
生物が持っている体の形や働きなどを形質といいますが、染色体異常などの明確な遺伝性疾患がなくても、親の有する歯や顎の形質が子供に遺伝し、歯並びに影響することがあります。
先天欠如歯
生まれつき歯が正常な数より少ない状態を先天欠如といい、不足している歯を先天欠如歯と言います。
左右両方ともではなく、片方だけ先天欠如が生じることがあり、その場合は歯列に左右差が生じてしまいます。左右両方とも欠損している場合は、左右のバランスは取れますが、対合歯との咬合関係に問題が生じます。
先天欠如歯の原因は遺伝疾患だけではありません。染色体異常が認められない親の子供でも、親に先天欠如歯が認められると子供にも生じることが多いことから、遺伝性疾患以外の遺伝的な影響もその原因の一つとして考えられています。
過剰歯
過剰歯は先天欠如の逆で、本来の歯の数よりも多い歯です。
歯列不正に関係する過剰歯の代表は、上顎の前歯の隙間である正中離開の原因となりやすい上顎正中過剰埋伏歯です。
過剰歯もその原因は明らかになっていませんが、親に過剰歯があると、その子供にも過剰歯が生えることが多い傾向があり、遺伝との関係性が指摘されています。
矮小歯
矮小歯は、歯の大きさの異常のひとつで、歯の大きさが正常よりも小さい歯を指します。
形そのままに小さくなっていることもあれば、円錐歯になっていることもあります。
矮小歯が生じると、審美性が良くないだけでなく、咬合関係にも問題が起こります。
矮小歯についても、遺伝性疾患が認められない親に矮小歯があれば、その子供にも生じることがあり、遺伝的影響を受けていると考えられています。
歯並びに影響を与える遺伝以外の要因
歯並びに影響を与えるのは、遺伝だけではありません。
歯の傾斜角や歯の位置、上下の歯の咬合関係なども歯列不正の原因となります。これらは生まれた後、すなわち後天的な要因と密接な関係性があります。
歯列不正に関係する後天的な要因としては、口腔習癖、生活習慣、さまざまな疾患などが挙げられます。
口腔習癖
口腔習癖は、歯並びに影響を与える癖の総称で、歯列に影響することから不良習癖ともよばれています。
舌癖
舌癖は、舌に関係する習癖です。多いのが、舌を前方に突出させる舌突出癖です。
舌先の本来の位置は上顎前歯部の歯肉付近なのですが、舌を前方に突出させると、下顎前歯を前方に向かって押すことになるので、前歯の唇側傾斜や開咬の原因となります。
舌の位置が下がっている低位舌でも同様の症状が生じえます。
吸指癖
吸指癖は、指を吸う習癖です。
乳児に見られる吸指癖は生理的なものと考えられていますが、幼児期を過ぎても続いている場合は不良習癖の一種とみなされます。
吸指癖を続けていると、上顎前歯の唇側傾斜と下顎前歯の舌側傾斜をきたし、開咬や上顎前突症を起こします。
咬爪癖(こうそうへき)
咬爪癖は、爪を噛む習癖です。
咬爪癖でも吸指癖と同様に上顎前歯が唇側傾斜するので、歯列不正をきたします。
口呼吸
口呼吸は、口で呼吸する習癖です。
ヒトの呼吸は鼻から行うのが正常なので、口呼吸は不良習癖のひとつになります。
口呼吸の原因はさまざまですが、いずれの原因の口呼吸であっても、口呼吸を続けていると前歯に口唇圧が加わらなくなり、前歯部の唇側傾斜や開咬などの歯列不正の原因となります。
咬唇癖
咬唇癖は、唇を噛む習癖です。
咬唇癖の歯列への影響は、どちらの唇を噛むのかによって異なります。
上口唇の咬唇癖では、上顎前歯の口蓋側傾斜と下顎前歯の唇側傾斜を起こして反対咬合になりますが、下口唇の場合は上顎前歯の唇側傾斜と下顎前歯の舌側傾斜による上顎前突になります。
いずれの場合も、開咬も同時に認めることが多いです。
咬合習癖
咬合習癖は、歯ぎしりや食いしばりなどの噛み合わせの癖の総称です。
歯ぎしりを続けていると、歯が全体的に唇側、頬側に傾斜し、歯間部に間隙の多い空隙歯列になりやすいです。
食いしばりでは、歯の咬耗による低位化により咬合関係が変化します。
生活習慣
歯並びに影響する生活習慣としては、次のようなものが挙げられます。
咀嚼習慣
顎の成長発育は、食べ物を噛む咀嚼習慣の影響を受けます。
下顎骨は、下顎頭という下顎骨の上部に成長発育の起点があります。下顎骨の成長発育期には、食べ物を噛んだときの刺激が下顎頭に伝わり、ここを適度に刺激することで、下顎骨の成長発育が促されると考えられています。
やわらかいものを好んだり、あまり噛まずに飲み込んだりすると、下顎骨の刺激が不足するので、下顎骨が十分成長できません。下顎骨の成長が不足すると、下顎骨が小さくなってしまいます。
咀嚼習慣は、顎の骨格の大きさや形にも影響を及ぼします。
異常嚥下癖
異常嚥下癖とは、食べ物や飲み物を飲み込むときに舌を前に出す習癖です。正常な嚥下では、舌は後方に位置します。
舌を前に出して飲み込む異常嚥下癖では、舌により上顎と下顎の前歯が前方に押されるため、開咬などの歯列不正の原因となります。
姿勢
姿勢が悪いと歯列不正を引き起こすことがあります。
例えば、頬杖です。
頬杖をつくと顎が横方向に押されますが、同時に歯並びも押されます。両手で頬杖をつくと横方向への圧迫は軽減されますが、その代わりに下顎骨が後方に押されます。
こうして、歯並びが悪くなっていきます。
この他、寝姿、猫背なども歯列不正の原因となります。
疾患
顎顔面部のさまざまな疾患の罹患状況も、歯並びに関係しています。
齲蝕症
齲蝕症すなわち虫歯を放置していると、やがて歯冠が崩壊し歯根だけになります。すると、その歯の隣在歯が傾斜してきます。一本でも歯が傾斜すると、その隣の歯も傾斜します。そして、対合歯が挺出し、歯並び全体が悪い方向に変化していきます。
これは永久歯だけでなく、乳歯においてもみられる現象です。
歯冠の崩壊が広範囲ではなく、わずかな範囲だけであっても、隣在歯の傾斜は起こりうるので、歯列不正の原因になります。
乳歯の早期喪失
乳歯は永久歯に生えかわります。
もし、適切な時期より早い時期に抜けることを早期喪失といいます。
乳歯を早期喪失し、そのままの状態でいると、抜けた乳歯の隣在歯が欠損部位に向けて傾斜します。対合歯は挺出します。このため、永久歯の萌出余地が減少し、永久歯の異所萌出をきたすことがあります。
乳歯の晩期残存
晩期残存とは、適切な時期を過ぎても生えかわらず、乳歯が残ったままになっていることです。
乳歯が晩期残存していると、永久歯の萌出が妨げられ、永久歯の異所萌出の原因となり、歯列不正を生じます。
耳鼻科疾患
歯並びには、耳鼻科の疾患も関係しています。歯並びに関係する耳鼻科の疾患は、鼻と咽頭に関する疾患です。
鼻の疾患としては、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎、慢性鼻炎、鼻中隔湾曲症など鼻閉を生じることが多い疾患が挙げられます。咽頭、すなわち喉の病気としては、アデノイド肥大症、扁桃肥大などです。
これらの疾患を罹患すると鼻詰まりが生じるので鼻呼吸が難しくなり、口呼吸になりやすくなります。このため、歯並びが悪くなってしまいます。
【まとめ】歯並びは遺伝するの?歯並びを悪くする生活習慣や悪癖も解説
歯並びと遺伝の関係について解説しました。
この記事では、下記のようなことがご理解いただけたのではないでしょうか。
ここがポイント!
- 歯並びは、遺伝の影響を受ける
- 歯並びに関係する遺伝性疾患もある
- 歯並びは、口腔習癖、生活習慣、さまざまな疾患など後天的な影響も受ける
- 口腔習癖には、舌癖、吸指癖、咬爪癖、口呼吸、咬唇癖、咬合習癖などがある
- 生活習慣には、咀嚼習慣、異常嚥下癖、姿勢などがある
- 疾患には、齲蝕症、乳歯の早期喪失、晩期残存、耳鼻科疾患などがある
歯並びの構成要素である歯や顎の形、大きさなどは遺伝の影響を受けます。
遺伝性疾患によって親から子へ伝わることもあれば、明確な遺伝性疾患がなくても形質として伝わることもあります。
また、歯並びは先天的影響を強く受けますが、後天的な影響もそれ以上に受け、歯並びは年々少しずつ変化していきます。このため、矯正治療では歯の動的治療により歯の位置を整えるだけでなく、歯列不正の原因の解消も重要なので、矯正治療の技術だけでなく、十分な専門知識や治療経験も要求されます。
歯並びで不安やお悩みのある方は、ぜひ当院にお越しください。