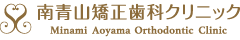歯の再建とは

人の歯は32本、親知らずである第三大臼歯を除くと28本あります。前歯、小臼歯、大臼歯、それぞれ歯の形が異なり、歯の持っている役割もまた異なります。
そして、例え失った歯が1本だけであったとしても、その歯が担っていた機能が失われることになります。この失われた歯の機能を、復活させるための歯科治療が歯の再建です。
現在では、歯を再建するためにさまざまな方法が開発されています。保険診療の適応を受けている歯の再建法もあれば、保険適用外の治療法もあります。
症状や治療を受ける方の希望に合わせて、最適な治療法が選べるようになっています。
歯がない状態(欠損歯)とは
歯がない状態(欠損歯)とは、何かしらの原因で歯が失くなる状態をいいます。天然の永久歯は通常上顎14本、下顎14本、合計28本が存在します。親知らずがある方だとプラス上下顎で4本、合計32本ある方もいらっしゃいます。
歯の構成としては上下前歯8本、上下犬歯4本、上下小臼歯8本、上下大臼歯8本となります。このいずれかが失くなった状態が欠損となります。
痛みを伴わなければ、歯を失ってもすぐに不自由はないかもしれませんが、放置することで様々な悪い影響が予想されます。歯を失ったら、早期の診断と治療が重要です。
歯がない状態(欠損歯)の症状とリスク

歯を失うとその歯だけではなく、周囲の歯にも影響がでてきます。時間が経つほどに様々な悪い影響を与え、治療方法も複雑になるため、歯を失った場合は早期治療を検討するようにしましょう。
咀嚼障害
歯の機能のひとつが、食べ物を噛む機能です。歯は食べ物を噛むために生まれてきたので、食べ物を噛むという機能は歯本来の機能といえます。
欠損歯が生じると、欠損部位で咬合できず、噛めなくなります。食べ物を噛むことができなくなるので、咀嚼機能に障害が生じます。
審美障害
人の第一印象を決める要素はさまざまですが、そのひとつが顔です。
顔の印象は目元だけでなく、口元からの影響を大きく受けています。口元の印象を決めるのが歯で、歯列の状態だけでなく、歯の有無も関係します。特に前歯の欠損があると、口元の印象が悪くなってしまいます。また、多数歯欠損症例では、口唇が落ち込むため老人性顔貌になってしまいます。
このことから、歯はヒトの審美性にも大きく関係しています。
構音障害
歯は構音器官のひとつですので、欠損歯の存在は発声にも影響します。
構音障害とは、構音器官の異常により、うまく発声ができない状態のことで、歯に原因のある構音障害を歯性構音障害といいます。
欠損歯の本数の増加に伴い、発語明瞭度も低下し、特にt音やd音、n音などの歯茎音が不明瞭になりやすく、唇を使って代替する傾向が指摘されています。
歯列不正の発症リスク
欠損歯を放置していると、欠損歯の隣接歯が欠損部位に向かって傾斜します。また、対合歯が挺出します。傾斜した隣接歯の隣接歯も傾斜しますので、歯列が少しずつ変化していきます。
このことから、欠損歯の状態は歯列不正のリスクが生じます。
胃腸障害
ヒトは食べ物を口腔内で咀嚼して、食塊を小さくすると同時に唾液を混ぜ合わせて、唾液に含まれる消化酵素を作用させます。こうして、嚥下しやすくするとともに消化もしやすくします。
欠損歯が生じると、咀嚼障害が生じる結果、食塊を小さくしたり唾液に混ぜたりすることが難しくなるため、胃腸での消化の負担が大きくなり、胃腸の不調をきたすリスクが生じます。
プラークコントロール不良
プラークコントロールは、歯の健康上の問題となるプラークを取り除くことです。
欠損部位の隣接歯の欠損側の歯面は、磨きやすそうですが実はそうではなく、意外と磨き残しが見られます。すなわち、欠損歯はプラークコントロール悪化の原因となります。
齲蝕症の発症リスク
齲蝕症の原因は、プラークの中に潜むストレプトコッカス・ミュータンスに代表されるレンサ球菌です。齲蝕の原因菌が産生する乳酸によって、歯が脱灰されることで齲蝕が発生します。
歯の欠損にともなうプラークコントロールの悪化は、齲蝕の発症リスクを高めます。
歯周病の発症リスク
歯周病は、歯を支える歯肉や歯槽骨が障害される疾患です。歯周病の原因も、齲蝕症と同じくプラークの中に潜む細菌です。
歯の欠損によるプラークコントロールの悪化は、歯周病の発症リスクにもつながります。
残存歯の負担増
欠損歯が生じると、残存歯で欠損歯の担っていた機能を代替します。すると、残存歯の咬合負担が増加するので、残存歯に加わる咬合圧も大きくなります。
欠損歯の増加に比例して、残存歯への負担も増加することで、残存歯の寿命も短くなってしまいます。
歯の喪失の原因

歯を喪失する原因、すなわち抜歯しなくてはならなくなる原因はさまざまです。
齲蝕症
齲蝕症は、齲蝕の原因菌が産生する乳酸によって歯が溶かされる病気です。
歯冠部分が齲蝕によって大きく崩壊し、歯肉縁下まで齲蝕が進行した病態を齲蝕症第4度と分類します。第4度まで齲蝕が進行すると、歯冠部分を修復することができないので、抜歯せざるを得なくなります。
歯周病
歯周病では、歯を支える歯周組織が破壊されていきます。特に重要なのが、歯を直接的に支えている歯槽骨という歯の周囲の骨です。
歯槽骨が歯周病により吸収されて減少すると、歯を支えきれなくなります。歯周病第4度という歯の周囲の歯槽骨が広範囲に吸収された状態にまで歯周病が進行すると、抜歯せざるを得なくなります。
根尖性歯周炎
齲蝕などを原因として、歯根の先端である根尖の周囲に病巣を形成したものが、根尖性歯周炎です。
根尖性歯周炎には根管治療が行われますが、根管治療の経過がよくなく、炎症を反復したり、上顎洞炎の原因となったりする場合は予後不良として抜歯します。
歯の外傷
転倒や衝突などにより、歯に強い外力が加わると破折することがあります。歯根部分の破折は、治療が非常に困難なので抜歯します。
また、完全に抜けてしまう完全脱臼は、脱臼直後なら再植により生着が期待できますが、時間の経過とともに生着率が低下します。再植しても生着が困難な外傷歯も抜歯となります。
腫瘍
腫瘍は、細胞が過剰増殖した組織で、良性と悪性の2種類に分けられます。この腫瘍も抜歯の原因となります。
例えば、下顎の臼歯部に好発するエナメル上皮腫という良性腫瘍です。エナメル上皮腫は摘出術が必要なのですが、隣接歯も同時に抜歯することがあります。
嚢胞
嚢胞は、内部に液体が貯留している袋状の病変です。嚢胞にはさまざまな種類がありますが、抜歯の原因として多いのが含歯性嚢胞です。
含歯性嚢胞は、智歯とも呼ばれる親知らずの歯冠に生じた嚢胞で、嚢胞の摘出と同時に原因歯の抜歯が必要となります。
埋伏歯
上顎正中過剰埋伏歯という、上顎の前歯の根のあたりに埋まっている余分な歯のように、歯列不正の原因となる埋もれた歯は抜歯する必要があります。
また、下顎の埋伏智歯という埋もれた状態の親知らずのように、炎症の原因になる智歯も抜歯します。
顎骨骨折
外傷による顎の骨折では、骨折線上に歯があることも珍しくありません。
骨折線上の歯のうち、埋伏歯、完全脱臼歯という抜けてしまった歯、歯根が折れた歯、歯周病が進んでいる歯は、骨折部分の感染の原因となるので抜歯します。
過剰歯
過剰歯は、正常よりも多い余分な歯です。
疼痛や腫脹などの炎症症状を認めなくても、歯列不正の原因となることがあります。歯列不正の原因となる場合は、抜歯が選択されます。
矯正治療
顎の大きさと比べて、歯の方が大きいことで歯列不正を起こしている場合、歯を並べるスペースを確保する目的で抜歯が行われることがあります。
矯正治療のための抜歯を便宜抜歯といい、原則的には第一小臼歯という前から4番目の歯が選ばれます。歯の状態によっては隣の第二小臼歯など、異なる歯が選択されることもあります。
放射線治療の予定照射野に生えている歯
舌がんや口腔底がん、喉頭がん、咽頭がんなどの治療では、放射線治療がしばしば行われます。これらの悪性腫瘍の放射線治療では、歯も放射線を受けます。
放射線治療後の抜歯は、放射線性顎骨壊死という治療の困難な骨壊死を起こす可能性があります。このため、将来的に保存が困難と予想される歯は、放射線治療前に抜歯します。
免疫能力の低下が予想される場合
悪性腫瘍や白血病などに対する抗がん剤を使った化学療法や臓器移植に伴う免疫抑制剤投与を受けると、病原微生物に対する免疫力が低下します。
自覚症状がないような慢性の歯周病であっても、免疫力の低下により急激に増悪し、骨髄炎や敗血症を起こすことがあります。
このような危険性が予想される場合は、治療前に抜歯することがあります。
歯の再建治療
欠損歯に対する再建治療には、さまざまな方法が開発されています。
ブリッジ(冠橋義歯)
冠橋義歯は、一般的にはブリッジと呼ばれる治療法です。
欠損部の前後の歯を支台歯として利用します。支台歯に装着したクラウン(冠)を支台装置とし、ポンティックと呼ばれる人工歯と連結した構造になっています。
保険診療でのブリッジは、原則的に金銀パラジウム合金で作られたものになります。
保険診療のブリッジは審美性に劣るので、自費診療になりますが、セラミック系材料を使って審美性を高めたタイプも作られています。
なお、ブリッジにより対応できる欠損歯は連続して2本までです。それ以上の欠損症例は、部分床義歯などブリッジ以外の方法となります。
全部床義歯
全部床義歯は、一般的には総入れ歯と呼ばれています。残存歯が全くなくなった状態での、咬合関係の回復を目的にしています。
保険診療での全部床義歯は、床をコンポジットレジンというプラスチックにしたレジン床義歯が多いです。
自費診療での全部床義歯は、床の部分に金属材料を広範囲に利用したものが多いです。
部分床義歯
部分床義歯は、残存歯がある場合に用いられる義歯です。残存歯を鉤歯として、クラスプという金具をかけて安定化させます。
部分床義歯は、保険診療でよく用いられるレジン床義歯、自費診療の床の部分に金属を採用した金属床義歯、クラスプを樹脂で作ったノンクラスプデンチャーなどがよく利用されています。
その他、残存歯のクラウンをクラスプの代わりとしたコーヌス義歯という部分床義歯もあります。
義歯は欠損歯の本数に制限はないのが利点です。一方、食後外して洗わなければならないことや寝る前は外さなくてはならないなど、使用上の手間がかかるのが難点です。
インプラント
インプラントは、顎骨にインプラントを埋入し、歯冠部分である上部構造とフィクスチャーを用いて連結した人工歯です。
ブリッジのように隣在歯を削合する必要もなく、部分床義歯のように使用上の手間もかかりません。インプラントは天然歯のような形態なので、審美性の点でも優れています。咬合関係についても、天然歯に匹敵するほどなのでしっかり噛めます。
歯の移植
歯の移植とは、保存不可能な歯を抜去した抜歯窩に、他の歯を抜歯して移植することです。
ドナーとなる歯は、第三大臼歯が選ばれることが多いです。歯の移植は、ご自身の歯を有効活用できるのが利点ですが、ドナーとなる歯の形や大きさ、歯根の形などの条件が厳しいのが難点です。
抜歯と同時に行われる歯の移植は、保険診療の適応を受けていますが、抜歯と歯の移植を別日で行う場合は保険適応外となります。
歯の再建治療のよくある質問
金属材料やコンポジットレジンを使う方法であれば、保険診療で受けられます。
ただし、審美性は良くないので審美性も同時に求めたい方は、セラミック系の材料を使える自費診療での歯の再建をおすすめします。
自費の入れ歯にはいろいろなタイプがあるので一概に言うのは難しいですが、自費の入れ歯で代表的な金属床義歯であれば厚みが薄いため、違和感も少なくてすみます。食べ物や飲み物の温度を感じやすく、美味しく食べられるという利点もあります。
保険診療の入れ歯はプラスチックで作られていますので、厚みがあり、違和感が大きいです。また、食べ物や飲み物の温度が伝わりにくいので、食べたときの感じに違和感もあります。
インプラント治療は、インプラントを顎の骨に埋める外科手術が必要です。
安全性の高い手術ですが、ステロイド治療や骨粗鬆症治療、がん治療などを受けている場合など、全身的な状態によっては受けられない場合があります。
歯の再建で最も審美性が高い方法は、インプラントです。天然歯と同じような形態で、かつ色調や透明感も得られます。
インプラント以外の方法では、セラミッククラウンを使ったブリッジ治療も審美性高く再建できます。
前歯と親知らずでは、歯の形や大きさが大きく異なるので、難しい場合がほとんどです。親知らずをドナーとして使う場合は、奥歯が適しています。