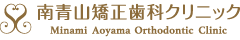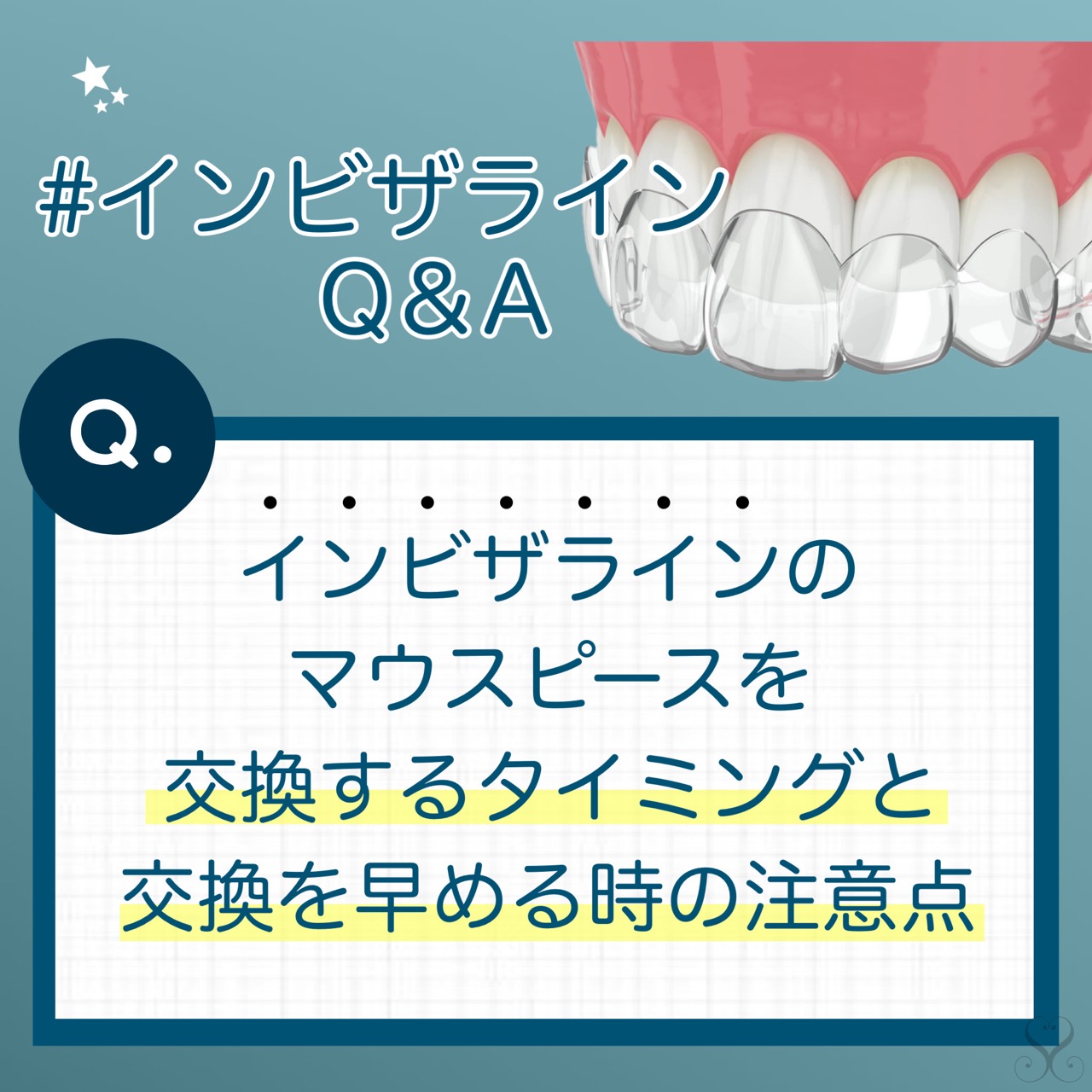インビザライン矯正で親知らずは抜く?抜かない?抜歯の必要性について
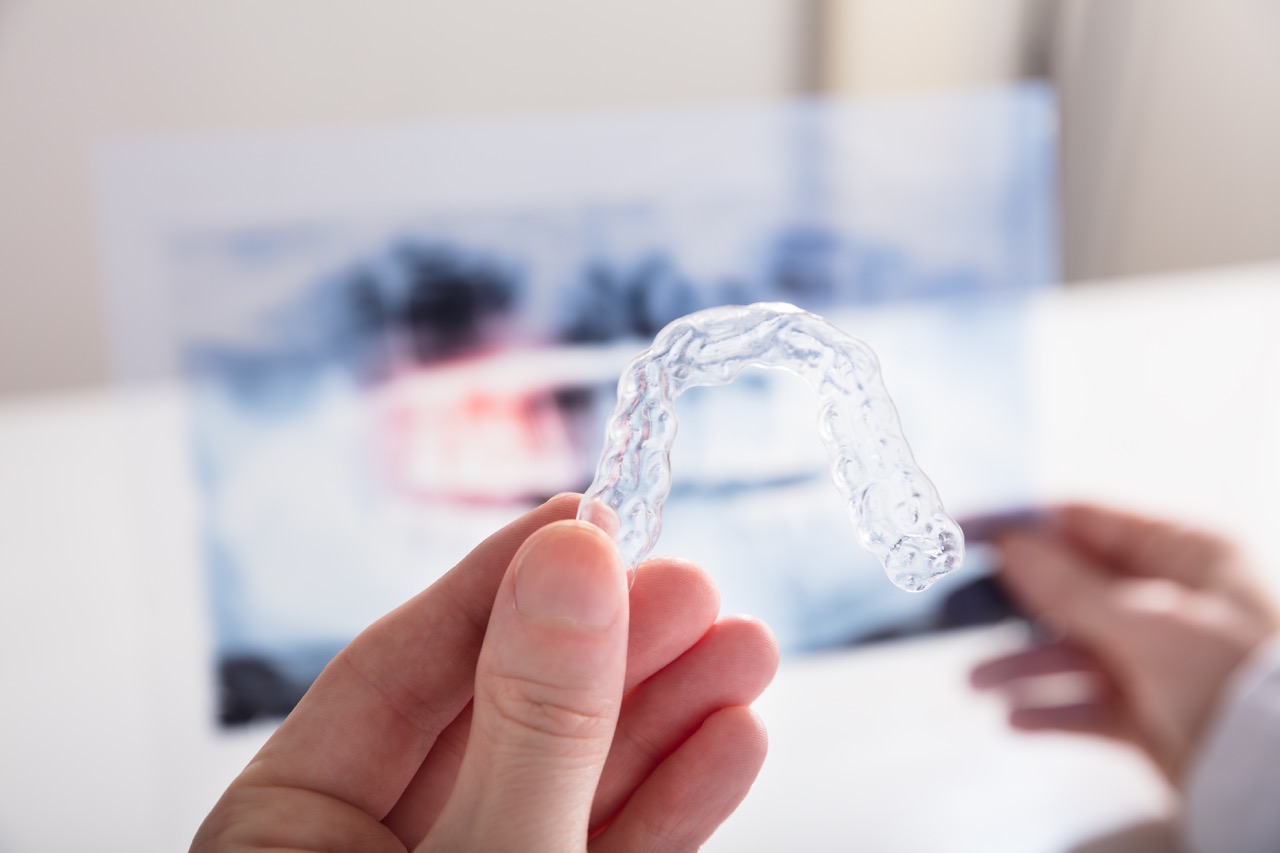
インビザライン矯正をスムーズに進めるためには、親知らずの管理が大切です。親知らずは、矯正治療に限らずさまざまな問題の原因となることが知られていますが、特にインビザライン矯正では治療への障害を避けるため抜歯を勧められることがあります。
「レントゲンで親知らずが埋まっていたので、抜歯を先にするよう勧められた」「何度も腫れたことがあったので、矯正治療の前に抜歯した」など、矯正治療を始めるにあたっては、親知らずが最初の課題ともいえるでしょう。
この記事では、インビザライン矯正と親知らずとの関係について解説します。
この記事を読むことで、インビザライン矯正で親知らずの抜歯の必要性やリスクについて理解でき、下記のような疑問や悩みを解決します。
こんな疑問を解消!
- 親知らずとはなにか
- 親知らずと歯並びにはどのような関係があるのか
- インビザライン矯正で親知らずを抜くのはなぜか
- インビザライン矯正開始前に親知らずの抜歯を判断する場合とは
- インビザライン矯正開始後に親知らずの抜歯を要する場合とは
- インビザライン矯正で親知らずを抜くタイミング
- インビザライン矯正で親知らずを抜くリスクとは
目次
親知らずとは
親知らずは『智歯』や『第三大臼歯』または『8番』とも呼ばれ、一般的には正中(顔の真ん中)から奥に向かって8番目の位置に萌出します。口腔内の一番奥(後方)に位置していて、最大で上下左右4本あって個人差があります。
そもそも、親知らずという名前の由来は「子どもが成長して親が知らないうちに生えてくる歯」「昔は平均寿命が短く、親が亡くなってから生えてくる歯」など諸説あります。
親知らずは顎が小さくなった現代人では、顎の骨の中に全部または一部が埋もれた「埋伏歯」や通常より小さい「矮小歯」など、通常とは異なる状態にあるケースも少なくありません。また、一番奥にあることから口腔ケアも難しく、虫歯や歯周病などのリスクが高い歯です。
親知らずと歯並びの関係
顎骨に十分なスペースがない場合、歯軸が斜めに傾いて萌出することがしばしばあります。その際、前の歯にぶつかるように傾いて萌出すると、隣接する歯に圧力がかかり、歯並びや咬合が乱れるなどの影響を与えることがあります。
歯軸が傾いて萌出した歯は、その後も前の歯を圧迫し続け、その力は時間をかけて奥歯だけでなく、前歯まで影響して全体の歯列が乱れることもあります。
インビザライン矯正で親知らずを抜く理由
インビザラインに限らず矯正治療を行う場合、親知らずの存在は注意が必要です。インビザライン矯正開始前に萌出していなかったとしても、レントゲンで親知らずが確認された場合、その傾きやサイズなどから治療に与える影響を予測して抜くことを検討することがあります。
そのまま放置して親知らずが歯列に悪影響を与えることになった場合、治療が計画通りに進まないばかりか、治療方針の変更や虫歯などの治療が必要になり、治療期間が長くなることも考えられます。
親知らずを抜くことは、治療を計画通りにスムーズに進めるための重要な判断のひとつとなるのです。
インビザライン矯正開始前に判断する場合
インビザライン矯正では、治療開始前にレントゲンなどの綿密な検査を基に治療方針を決定します。その際に、親知らずを抜くか抜かないかの判断をすることが多いでしょう。
ここでは、判断の根拠となるさまざまなケースについて説明します。
インビザライン矯正で親知らずを抜くケース
インビザライン矯正で親知らずを抜くケースについて解説します。
親知らずが前の歯を押している
親知らずが傾いて萌出している場合、その力によって歯列が乱れることがあります。インビザライン矯正によって歯を動かしても後方から押す力がかかるため、適切な位置からずれたり、早期に後戻りする可能性が高くなります。
正常な咬合の障害になっている
親知らずの萌出によって、咬合がずれるなどの悪影響を与えることがあります。そのため、審美的な問題だけでなく顎関節に負担がかかり、顎関節症の原因となったり、咀嚼がうまくできず消化不良の原因となったりすることがあります。
歯を並べるスペースを確保できない
インビザライン矯正では、乱れた歯列を並べるためのスペースを必要とするケースも少なくありません。
親知らずがあることで歯を後方に移動できるスペースを確保できず、適切に歯を並べることができないことがあります。
腫れや痛みを繰り返している
親知らずには、歯の周囲が腫れたり痛んだりする「智歯周囲炎」や「虫歯」がしばしば見られ繰り返す傾向にあります。腫れや痛みで口が開かなくなることもあり、早期に適切な治療が必要となるため、その間は矯正治療を中断することになります。
虫歯の原因となっている
親知らずは、口腔内の最も奥に萌出するため歯ブラシが届きづらく、また斜めに生えると接触している歯との間に深い隙間ができて汚れが溜まってしまうケースが見受けられます。
親知らずと隣接歯との間は見えづらく、かなり進行するまで気づかないこともあるため、虫歯の有無に限らずリスクがある場合には抜くことが推奨されます。
インビザライン矯正で親知らずを抜かないケース
インビザライン矯正では、親知らずを抜かないケースもあります。
ここでは、どのような場合に抜かなくてもよいのか具体的に紹介します。
歯並びに影響を与えていない
親知らずが適切に萌出していて、咬合や歯並びに悪い影響を与えていないケースや虫歯や歯周病のリスクが少なく、通常の歯と同じように機能できると判断された場合には抜歯は不要です。
ただし、清掃性は悪いので定期的な管理をすることが大切です。
上下がきちんと咬合できている
咬み合う歯と適切に咬合しているかは、とても重要なポイントです。
親知らずであっても対合する歯ときちんと咬合できていて、他の歯の咬合に影響を与えていない場合は、あえて抜く必要はありません。
他の方法で歯を並べるスペースを確保できている
歯を移動するスペースの確保が必要なケースで、IPR(歯の隙間の削合)で対応できる場合には親知らずを抜かない選択肢もあります。
ただし、IPRで対応できるのは軽度から中度の歯列不正の場合であり、重度の歯列不正で大きくスペースが必要な場合には抜くことが推奨されます。
奥歯を遠心方向に動かす必要がない
親知らずが正常に萌出していて、インビザライン矯正で奥歯を遠心方向(後方)に移動させる必要がない場合には、親知らずを抜かないという選択肢もあります。ただし、親知らずに由来する何らかの障害が予測される場合には、抜くことが推奨されることがあります。
根が未完成
親知らずが未成熟で完全に根まで完成していない場合は、歯並びには影響しないことが多く親知らずを抜かないケースもあります。
このようなケースは若い方に見られますが、成長と共に根が形成されるため、レントゲン撮影で継続的に確認し判断していくことが重要です。
完全に埋伏している
親知らずが顎骨の中に完全に埋まっていて、萌出する見込みがない場合や埋まっている親知らずの大きさや位置によって抜歯のリスクの方が大きい場合には、抜かない選択をすることがあります。
ただし、インビザライン矯正への影響が予測される場合は、基本的に抜くことが推奨されます。
インビザライン矯正開始後に親知らずの抜歯の判断を要する場合
インビザライン矯正を開始してから、何らかの理由で親知らずを抜くケースについて説明します。
インビザライン矯正期間中に親知らずを抜くケース
親知らずがインビザライン矯正中に萌出してきて、治療に影響を与えることが懸念される場合には、治療を中断して親知らずを抜くことがあります。
根が未完成な親知らずを抜歯せず、インビザライン矯正を開始した場合などに、このようなケースがみられます。
また、親知らずが炎症を起こしたり、虫歯になったりして悪影響がある場合、治療期間中に限らず抜くことがあります。
インビザライン矯正の保定期間中に親知らずを抜くケース
治療前や治療中に親知らずを抜歯せず残していて、保定期間中に炎症や虫歯などの問題が起こった場合には、保定期間中に抜くことがあります。また、親知らずが矯正治療中にまだ顎骨の深い位置にあり、抜くことによるリスクが高く、リスクを下げるためにある程度表面近くまで萌出するのを待って抜くことがあります。このような場合には、抜くタイミングが保定期間中にかかることがあります。
歯が正常に萌出していれば抜く必要がない場合もありますが、後戻りの防止に関係するため親知らずの管理は重要となります。
インビザライン矯正で親知らずを抜く最適なタイミング
インビザライン矯正で親知らずを抜くのは、基本的に治療開始前が最適なタイミングとされています。親知らずの存在によって、歯並びや咬合、歯の移動など、治療にかかるさまざまなシーンで影響を与えることが多く、治療計画を障害される可能性があるためです。
ただ親知らずの本数には個人差があり、すべての親知らずの抜歯が終了してからインビザライン矯正を開始することが多いので、本数によっては治療開始までに時間がかかることは理解しておきましょう。
親知らずをすべて抜いてからインビザライン矯正を開始すると、比較的計画に沿ってスムーズに治療を進められます。
インビザライン矯正で親知らずを抜くことによるリスク
親知らずに限らず、抜歯にはリスクを伴います。
インビザライン矯正においても、親知らずを同様に抜くことによるリスクがあることは、事前に理解しておく必要があります。
術後の腫れや痛み、出血
親知らずの抜歯は外科手術です。萌出の仕方によっては、切開や分割抜歯(歯をいくつかに分割して抜く方法)、顎骨の切削が必要で、術後の腫れや痛み、出血があるケースは多いでしょう。
術中は麻酔下にあり、術後は抗生剤や鎮痛剤などが処方され、圧迫止血で出血も抑えられますが、術後の症状には個人差がありますので、状況に合わせた対応を行います。
術後の開口障害
親知らずの抜歯は手術になるため、術後の炎症などによって口が開きにくくなることがあります。食事がしづらく、咀嚼もうまくできない場合がありますが、徐々に改善していきます。
抜歯窩(抜歯後の穴)に食物が詰まる
親知らずを抜くと、顎骨と歯肉に穴ができて完全に塞がるまでには時間を要し、食物が入り込んで詰まってしまうことがあります。もし詰まったまま放置すると、細菌感染による炎症や口臭などの原因となります。
抜歯後の傷がある程度回復したら、よくうがいをしたり、歯科医院を受診して洗浄したりしてもらうことをおすすめします。つまようじや歯間ブラシなどでつつくことは避けましょう。
ドライソケット
ドライソケットは、「抜歯窩治癒不全」とも呼ばれます。
通常歯を抜くと、そこに「血餅」というカサブタのような組織が作られて治癒を促進しますが、何らかの理由で血餅が剥がれて骨が剝き出しになった状態になることをドライソケットといいます。
ドライソケットは回復傾向にあった抜歯後の傷が再び痛み始め、わずかな刺激でも激痛が続きます。ドライソケットから顎骨が細菌感染することもありますので、早めに対処することが必要です。
矯正治療の担当医では抜けないことがある
矯正治療専門のクリニックでは、抜歯を一般歯科や口腔外科に紹介することがあります。特に親知らずでは、埋伏歯や根が湾曲している歯、顎骨の深い位置にある歯のような難抜歯が予測されるケースや基礎疾患がある患者様は、リスク回避や緊急時の対応などを鑑みて設備の整った大学病院などの口腔外科専門外来に紹介されることが多いでしょう。
稀に神経や血管を傷つけることがある
特に下顎の親知らずは下顎管という神経と血管の通り道に近接することが多く、入念な検査と細心の注意を払って行われますが、稀に損傷してしまい、麻痺や大量出血を引き起こすことがあります。
これらのリスクを回避するために、親知らずの抜歯は歯の状況によって設備の整った口腔外科専門医で行うことが推奨されます。
【まとめ】インビザライン矯正で親知らずは抜く?抜かない?抜歯の必要性について
インビザライン矯正と親知らずの関係について解説しました。
この記事では、下記のようなことが理解できたのではないでしょうか。
ここがポイント!
- 親知らずとは、口腔内の一番奥にあり、埋伏歯や矮小歯など、通常とは異なる状態にあることが多く、口腔ケアも難しいため虫歯や歯周病のリスクが高い
- 親知らずが斜めに萌出して隣接する歯に圧力をかけると、歯並びや咬合が乱れるなど、歯列全体に影響を与えることがある
- 親知らずが歯列に悪影響を与えることによって、治療の遅れや計画の変更、期間の延長などが予測された場合には、抜歯を検討することがある
- インビザライン矯正治療開始前に親知らずを抜くケースは以下の通り
・親知らずが前の歯を押している:後方から圧力がかかり歯列が乱れることがある
・正常な咬合の障害になっている:咬合のずれや顎関節症などの原因になることがある
・歯を並べるスペースを確保できない:歯を後方に移動できず治療の障害になることがある
・腫れや痛みを繰り返している:清掃がしにくく炎症による腫れや痛みを繰り返すことがある
・虫歯の原因となっている:親知らずの位置や傾きから清掃がしにくく虫歯になりやすい - インビザライン矯正治療開始前に親知らずを抜かないケースは以下の通り
・歯並びに影響を与えていない:適切に萌出して他の歯に圧力をかけていない場合
・上下がきちんと咬合できている:きちんと萌出して上下が適切に咬合している場合
・他の方法で歯を並べるスペースを確保できている:IPRなどで対応できる軽度から中度の歯列不正の場合
・奥歯を遠心方向に動かす必要がない:治療にかかる奥歯の後方移動が不要な場合
・根が未完成:未成熟な場合、抜かずに継続管理で判断することがある
・完全に埋伏している:完全に顎骨の中に埋まって萌出する見込みがない場合や抜歯のリスクの方が高い場合 - インビザライン矯正治療中に抜歯するケースとして、治療中に萌出した場合や根の完成を待っていた場合、炎症が起こった場合が挙げられる
- インビザライン矯正の保定中に抜歯するケースとして、親知らずの存在は確認していたが、抜歯せずに残していた場合や顎骨の深いところにあってリスク低下の時期を待っていた場合が挙げられる
- インビザライン矯正で親知らずを抜くタイミングは、治療をスムーズに進めるためにも矯正治療開始前が最適とされている
- インビザライン矯正で親知らずを抜くリスクは下記の通り
・術後の腫れや痛み、出血:外科手術のため腫れや痛み、出血が多くみられる
・術後の開口障害:術後の炎症などで口が開かなくなるが、徐々に改善するのが一般的
・抜歯窩に食物が詰まる;抜歯後の穴に食物が詰まり、炎症の原因となることがある
・ドライソケット:抜歯後の傷から血餅が取れて骨が剥き出しになり、強い痛みなどが起こる
・矯正治療の担当医では抜歯に対応していないことがある:矯正専門医では抜歯を行わず一般歯科や口腔外科、状態によっては設備の整った口腔外科専門医に紹介することがある
・稀に神経や血管を傷つけることがある:特に下顎の場合、神経や血管を損傷して麻痺や大出血などが稀に起こることがある
親知らずは、トラブルを引き起こすことの多い歯です。インビザライン矯正でも矯正治療に悪影響を与えるリスクがあることから、しばしば抜歯を推奨されます。
ただし、必ずしも抜歯が必要というわけではなく、レントゲンなどの詳細な検査を基にインビザライン矯正治療に与える影響を予測して判断されます。もし、抜歯を推奨された場合は、治療への影響の大きさやリスクを理解して抜歯に臨むことが大切です。
南青山矯正歯科クリニックでは、治療開始前に綿密な検査を行い、治療計画を立てます。検査によって抜歯が必要と判断した場合には、抜歯の対応も行える歯科医師が常駐しております。
インビザライン矯正治療を検討されている方には、現状や予測について丁寧にご説明しておりますのでお気軽にご相談ください。