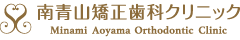不正咬合とは

不正咬合とは、正常咬合以外の噛み合わせの総称です。
正常咬合は、食べ物を噛む咀嚼機能に代表される顎口腔機能を保つことができる咬合関係を指します。したがって、正常な咬合が得られない不正咬合では、正常な顎口腔機能を営み、健康を維持することが困難となり、何らかの障害や病的変化をきたすようになります。
不正咬合は正常咬合でない咬合の総称なので、その原因や症状は非常に多岐にわたります。審美面だけでなく、健康面からも不正咬合の治療の需要は高く、原因や症状などに応じて、さまざまな治療が開発されています。
正常な咬合(正しい咬み合わせ)とは
不正咬合を考える上で避けて通れないのが、『正常な咬合とは一体何か』です。
正常な咬合は、単に歯や歯並びの形態と審美性が優れた咬合関係にとどまりません。正常な咬合とは、歯や歯周組織、顎骨、顎関節、筋肉などの大きさや形、位置、方向などが相互にバランスが取れて、スムーズで調和のある動きが可能な咬合関係を指します。
すなわち正常な咬合とは、顎口腔機能に異常を生じさせることなく、咀嚼に関わるあらゆる器官の健康状態を長期にわたって保つことができる咬合といえます。
不正咬合の症状とリスク
顎口腔機能に異常を生じさせる不正咬合は、放置しているとさまざまな症状やリスクが生じます。
咀嚼作用の困難化
食べ物を咀嚼するためには、上顎と下顎の歯の間に食べ物を適切に配置しなければなりません。
不正咬合では歯列の乱れや対合関係のずれにより、咬合面間に食べ物を適切に配置することが難しくなります。また、咀嚼のための顎運動も不自然になります。
不正咬合ではこれらの理由により、正常歯列と比べて咀嚼作用が困難化します。
咀嚼能率の低下
臼歯の本数が低下するほど、咬合面の接触面積が低下するため、咀嚼能率は低下します。
不正咬合の歯列では歯数が足りていても、臼歯部の咬合接触面積が低下したり、歯の接触方向が不良になったりします。
このため、正常歯列と比べると咀嚼能率が低下します。
構音障害
歯、特に前歯は発音に大きな関係性を有しています。
具体例を挙げると、前歯部開咬や著しい上顎前突症、反対咬合では、サ行やザ行などの発音が甘えたような声の発音になりやすいです。
前歯ほどではありませんが、臼歯部も発音に関係しており、臼歯部の空隙歯列では発声時に空気が漏れることで、言葉の不明瞭化が指摘されます。
顎口腔の発育障害
不正咬合の中には、成長発育段階に生じることで、顎の骨格の成長発育に強く影響します。例えば、小児の開咬では小児の段階では歯に原因のある歯性の開咬だったものが、放置していると骨格性の開咬になることが知られています。また、交叉咬合は顎の骨格を左右非対称にしますし、過蓋咬合は前方への顎骨の成長発育を不十分にします。
このように、不正咬合は顎の形態形成に影響し、歪みの原因になります。
齲蝕症のリスク
歯列不正では、隣接歯同士の頬舌的な位置のずれにより重なり合う部分が増えるため、自浄作用が低下するだけでなく、ブラッシングも困難化します。
齲蝕症の原因は、プラークの中に潜むストレプトコッカス・ミュータンスなどの細菌です。
歯間部を中心にプラークが残りやすくなるため、齲蝕症の発症リスクが増加します。
歯周病のリスク
歯周病の原因も齲蝕症と同じく、プラーク中の細菌です。
不正咬合による自浄作用の低下やブラッシング困難化により、プラークが停滞しやすくなることに加え、咬合圧の付加方向の異常などもあり、歯周病のリスクも増大します。
不正咬合の悪化リスク
齲蝕症で歯冠が崩壊したり、歯周病で歯が脱落したりすると、隣接歯の移動や対合歯の挺出を招来します。
移動や挺出を生じた部分を中心に、新たな不正咬合をもたらすリスクが高まります。
顎関節症のリスク
不正咬合では上顎と下顎の接触関係が悪化し、顎の運動経路を歪ませます。この結果、顎運動に関係する筋群や顎関節に異常な負荷を及ぼします。
この状態が長期にわたって持続すると、顎関節症や咀嚼筋群の筋肉痛などを引き起こします。
外傷のリスク
不正咬合により、唇側に傾斜したり転位したりした前歯は、転倒や衝突などの外力を受けやすくなります。
外傷による打撲を受けた結果、外傷歯の破折や脱臼、脱落を生じることがあるだけでなく、傾斜や転位した歯が口腔粘膜を傷害することもあります。
胃腸疾患のリスク
人は食べ物を咀嚼して小さくすると同時に唾液と混ぜ合わせることで、唾液に含まれる消化酵素を作用させやすくします。こうして、食べ物を胃腸で消化しやすくするのですが、不正咬合では咀嚼作用が困難化するため、食べ物を適度な大きさに加工することが難しくなります。
このため胃腸での消化に大きな負担がかかり、胃腸の不調をきたすリスクが生じます。
審美的障害
人の第一印象は顔貌に左右されますが、笑顔だけでなく口元の外見も顔貌の重要な要素です。それらを構成する歯や歯列は、人に与える印象の上で重要な役割を果たしています。
不正咬合の歯や歯列では笑顔や口元の印象を悪くするため、審美性の低下も問題とされます。実際、矯正歯科を受診する動機の中で最も多い主訴が審美的な問題です。
心理的障害
他人に与える印象、特に顔貌は社会生活を営む上での重要な要素です。
不正咬合による顔貌の審美性の低下や構音障害は、自分が劣っているという観念をはじめとして、心や性格に大きな影響を与えます。
歯科治療の困難化
不正咬合により、歯列の形態や咬合関係に異常があると、その部位の齲蝕治療が必要になった場合にその処置が困難になります。
歯冠修復処置が難しくなると同時に歯の削除範囲も広くなり、治療に伴う歯への侵襲も増大します。
口腔乾燥症の発症リスク
不正咬合によっては、口唇の閉鎖が難しくなることがあります。口唇が閉鎖しなければ、口腔内の唾液が蒸発しやすくなります。
唾液分泌能に異常がなくても、蒸発することで唾液が失われ口腔内が乾燥化します。
口臭
口臭の原因の大多数は、口腔内の細菌や汚れです。
唾液には、歯や口腔内の汚れの洗浄作用や口腔内細菌への抗菌作用がありますが、口腔内の乾燥化により、それらが低下します。
不正咬合による自浄作用の低下も加わり、歯や口腔内での汚れや細菌の活動性の増加により、口臭のリスクが高まります。
歯の寿命への影響
正常咬合と比べると、不正咬合を長期にわたって放置していると、歯の寿命が短くなるリスクがあります。齲蝕症や歯周病、外傷リスクの増加、歯科治療の困難化は、すべて歯の寿命に関係するからです。
不正咬合の治療は、歯を長持ちさせるためにも、早期治療がおすすめです。
不正咬合の原因
不正咬合の原因は、先天的か後天的か、歯性か骨格性かなど、非常に幅広いという特性を持っています。
歯の先天欠如
歯の先天欠如は、歯の本数が正常な数より少ない状態です。
永久歯では、下顎の第二小臼歯、上顎の第二小臼歯、上顎の側切歯に多く見られ、これら3歯が永久歯の先天欠如の90%弱を占めます。
男女間に性差はなく、歯の先天欠如のほとんどが優性遺伝によるものと考えられています。
過剰歯
過剰歯は、正常な数よりも多い余分な歯です。一般的に2〜3%ほどの頻度で認められ、男性に多く、原因はわかっていないのが現状です。
過剰歯は、上顎の正中部と上顎の大臼歯部に生じやすい傾向があります。
歯の形態異常
歯の形態異常は、歯冠の形や歯根の数の異常だけでなく、正常な2本の歯が合体した癒合歯や正常な歯と過剰歯が合体した双生歯も含まれます。
永久歯の形態異常としては、上顎の側切歯が円錐状に小さくなっている栓状歯の発生頻度が多いです。
歯の大きさの異常
不正咬合の原因になりうる歯の大きさの異常としては、歯が異常に大きいメガドンティア(megadontia)、反対に異常に小さいミクロドンティア(microdontia)があります。歯の大きさの異常は、遺伝的な影響を強く受けて生じると考えられています。
メガドンティアやミクロドンティアほどの異常ではなくても、顎の大きさに対して、歯が大き過ぎれば叢生に、小さ過ぎれば空隙歯列になります。
遺伝
進化の過程で見ると、人類の上顎骨や下顎骨は縮小傾向にありますが、骨や歯の大きさや形には差異があり、それぞれ遺伝の影響を強く受けていると考えられています。
例えば、一方の親から小さな顎を受け継ぎ、もう一方の親から大きな歯を遺伝すれば、その子供には顎の骨格と歯の大きさにアンバランスが生じます。このように遺伝も不正咬合の原因と考えられています。
全身的原因
不正咬合に関係する全身的な原因としては、内分泌疾患や栄養障害が挙げられます。
内分泌疾患としては、顎の骨格の成長発育に影響する成長ホルモンが関係しており、分泌亢進なら下顎の骨末端肥大症、分泌不全なら小顎症を引き起こします。
栄養障害としては、ビタミン類の不足による顎の発育不全が代表的です。
歯の交換の錯誤
歯の交換の錯誤とは、乳歯から永久歯への歯の交換、すなわち生え替わりに際しての問題です。乳歯がいつまでも抜けない晩期残存や、乳歯が適切な時期より早く抜ける早期喪失などが挙げられます。
乳歯の晩期残存では、永久歯が頬側、あるいは舌側に萌出することが多いです。一方、乳歯の早期喪失で問題となるのが、永久歯の正常な萌出時期より6か月以上早い脱落です。これほど早い時期に乳歯が脱落すると、永久歯の萌出余地が不十分になってしまうことが多いからです。
このように、乳歯の脱落するタイミングも不正咬合の原因になります。
歯の萌出障害
歯の萌出障害とは、歯の正常な萌出が阻害されることです。
歯の萌出障害の原因としては、歯の交換の錯誤のほか、顎骨内に生じる歯牙種という歯の良性腫瘍、過剰歯、嚢胞という内部が液体で満たされた出来物などが挙げられます。
なお、歯の萌出障害は、乳歯に認められることは稀です。
不良習癖
不良習癖とは、歯列に悪影響を及ぼす口腔習癖の総称です。舌を前方に出す舌突出癖、舌が下がる低位舌、口で呼吸する口呼吸、指をしゃぶる吸指癖、爪を噛む咬爪癖、唇をかむ咬唇癖など、さまざまな不良習癖があります。
不良習癖と不正咬合には強い関係性があり、歯性及び骨格性の不正咬合の原因となることが指摘されています。
不正咬合の種類
不正咬合の症状は多様です。
したがって、咬合からみた不正咬合、咬合面観からみた不正咬合、歯列形態からみた不正咬合などさまざまな視点から分類されています。
過蓋咬合
過蓋咬合は、上顎前歯部と下顎前歯部の垂直被蓋が異常に深く、下顎前歯が上顎前歯で隠れてしまっている不正咬合です。
このため、英語では噛み合わせが深いという意味からdeep overbiteといいます。
著しい過蓋咬合では、下顎前歯の切端が上顎前歯の舌側歯肉を噛むほどになっていることもあります。また、反対咬合でも過蓋咬合は発症し、反対咬合の過蓋咬合では、下顎前歯部によって上顎前歯部が見えなくなっています。
切端咬合
切端咬合は、上顎前歯の切端と下顎前歯の切端が咬合している不正咬合です。
切端同士が触れ合うということから英語では、edge-to-edge biteと呼ばれます。
反対咬合
反対咬合は、下顎の歯が上顎の歯を外側から取り巻くように噛み合わせている不正咬合で、上顎と下顎の被蓋関係が逆になっています。
反対咬合というと、前歯部の被蓋関係だけに着目しがちですが、前歯部の被蓋関係は問題なく、臼歯部の被蓋関係だけが逆になっている場合も反対咬合といいます。
開咬
開咬は、複数の上顎と下顎の歯が咬合すべき歯と連続して噛み合わせられない不正咬合です。
前歯部の開咬がイメージされがちですが、臼歯部に生じることもあり、前歯部開咬に対して臼歯部開咬と呼ばれます。なお、通常は1歯だけの離開状態では開咬とは認められません。
交叉咬合
交叉咬合は上顎と下顎の歯列が、どこかで交叉する不正咬合です。交叉点は1箇所とは限らず、複数箇所で交叉することもあります。
例えば、臼歯部の反対咬合が両側に生じ、前歯部の被蓋関係が正常であれば、2箇所に交叉咬合が生じていることになります。
下顎遠心咬合
下顎遠心咬合は、上顎の歯列弓に対して、下顎の歯列弓が正常な位置よりも後方、すなわち遠心に位置している不正咬合です。
なお、上顎と下顎の咬合関係を比較したもので、下顎骨の形態異常があるとは限りません。
下顎近心咬合
下顎近心咬合は、下顎の歯列弓が上顎の歯列弓よりも前方、すなわち近心に位置している不正咬合です。
下顎遠心咬合と同じく、必ずしも下顎骨の形態異常を伴うわけではありません。
上顎遠心咬合
上顎遠心咬合は、下顎の歯列弓の位置は正常だが、上顎の歯列弓が下顎の歯列弓よりも遠心に咬合している不正咬合です。
下顎近心咬合と非常によく似ているので、習慣的に下顎近心咬合と同一視されることもあります。
上顎近心咬合
上顎近心咬合は、下顎の歯列弓の位置が正常な位置にあるのに対し、上顎の歯列弓が近心に位置している不正咬合です。
上顎遠心咬合と同じく、下顎遠心咬合と習慣的に呼ばれることも多いです。
叢生歯列
叢生歯列は、歯の唇舌的、もしくは頬舌的な転位や傾斜、もしくは回転がたくさんの歯に連続して生じる、または1歯を隔てた歯同士に認められる不正咬合です。一般的には乱杭歯として知られています。
咬合面からみると、歯列がスムーズなカーブを描かず、凸凹とした歯並びになっています。
空隙歯列
空隙歯列は、たくさんの歯間に空隙が生じている不正咬合です。
歯の大きさが顎骨の大きさに対して、小さすぎる場合や舌圧により歯が唇側や頬側に傾斜した場合などに生じます。
空隙歯列は、歯間部の複数の空隙を指し、一箇所だけ空隙がある場合は空隙歯列とは診断されません。
正中離開
正中離開は左右側の中切歯が接触せず、中切歯間に空隙が見られる不正咬合です。
左右両方とも中切歯が遠心に傾斜していることもあれば、どちらか一方の中切歯だけ遠心に傾斜して生じていることもあります。
一般的に正中離開は、上顎の中切歯間に適用され、下顎の中切歯間の空隙には用いられません。
移転
移転は、歯の並ぶ順序が間違っている不正咬合です。
一例を挙げると、上顎の側切歯(2番目の歯)と犬歯(3番目の歯)や上顎の犬歯と第一小臼歯(4番目の歯)の位置が反対になっていたりする歯並びです。
なお、このような歯は移転歯と呼ばれます。
狭窄歯列弓
狭窄歯列弓とは、臼歯部の歯が舌側に傾斜していたり、もしくは舌側にずれて生えてきていたりすることで、歯列弓の臼歯部の横幅が狭められた歯並びです。
前歯部の歯の傾斜やずれはほとんどありません。
V字型歯列弓
V字型歯列弓は、狭窄歯列弓ととてもよく似ていますが、狭窄歯列弓と異なり、前歯部の歯並びも狭くなり、唇側転位や回転を生じ、歯列弓がV字型に見える歯並びです。
下顎は稀で、主に上顎に生じます。
鞍状歯列弓
鞍状歯列弓はV字型歯列弓と異なり、下顎に生じやすい不正咬合です。
小臼歯という前から4〜5番目あたりの歯が舌側に転位することで、鞍のような形に見える歯並びです。
方形歯列弓
方形歯列弓は前歯部の歯が舌側に転位し、直線上に並んだ歯並びです。
上からみると、箱のような形に見えることから、このように名付けられました。
不正咬合の治療法
不正咬合の治療法は、症状や原因、年齢に応じてさまざまな方法が開発されています。
ワイヤー矯正・マルチブラケット矯正
ワイヤー矯正は、全歯にブラケットやバンドを装着し、弾性ワイヤーやエラスティックの作用で歯の移動を図る矯正治療法です。
現在主流のエッジワイズ法では、歯を平行に移動させる歯体移動を行いながら、歯を三次元に移動させられるのが特徴です。このため、ほぼ全ての不正咬合の治療に適応があります。
その一方、複雑な構造の矯正装置が装着されるので、目立ちやすい、食事やブラッシングがしにくいなどの難点があります。
マウスピース矯正
マウスピース矯正は、アライナーと呼ばれるマウスピースを矯正装置とした矯正治療法です。マウスピースを一定の間隔で新しいものに交換することで、歯を移動させます。
マウスピースは薄く透明度が高く、歯に緊密に適合するため目立ちにくいです。また、食事や歯磨きのときに外せるのが利点です。
反面、装着時間が短いと効果が出ない、歯の移動が傾斜移動になりやすい、挺出や圧下が困難などの難点もあります。挺出や圧下など、マウスピース矯正では難しい歯の移動は、アタッチメントという歯の表面につける突起物を設置することで対応します。
インプラント矯正
インプラント矯正は、歯科用アンカースクリューという小さなネジ状の矯正装置を口腔内に設置し、そこを支えとしてエラスティックの作用で歯の移動を図る矯正治療法です。
一般的な矯正治療法では、大臼歯を支えにするため、大臼歯が動くと困りますので、強い力はかけられません。しかし、アンカースクリューは任意の場所に打てるので、最適な矯正力を最適な方向からかけられます。
このため、効率的な歯の移動が可能となり、矯正治療の治療期間の短縮も期待できます。
顎矯正手術
顎矯正手術は、上顎骨や下顎骨の変形によって生じた不正咬合の治療に用いられる骨切り手術です。具体的には、骨格性下顎前突症、骨格性上顎前突症、開咬、上顎骨狭窄症、口唇口蓋裂などです。
手術対象年齢は、顎骨の成長発育が終了した18〜20歳以降です。
上顎骨に対するものとしては、ル・フォー(Le Fort)Ⅰ型骨切り術や上顎前歯部歯槽骨骨切り術、下顎骨に対するものとしては、下顎枝矢状分割術や下顎枝垂直分割術などがあります。
セラミック矯正
セラミック矯正はセラミッククラウンの形態によって、前歯部の歯列の審美性を改善させる治療法で、クラウン(補綴物)を使うことから補綴矯正と呼ばれています。
セラミッククラウンを使うため、歯列矯正と比べて治療期間が大幅に短縮できるうえ、歯の形態や色調も同時に改善できるのが利点です。
一方、歯を削合しなければならない、咬合圧の方向と歯根の方向が一致しないので歯の破折リスクがある、セラミッククラウンには寿命があるなどのデメリットもあります。
筋機能療法
筋機能療法は、口腔周囲筋の機能異常を改善したり、口腔周囲筋の筋機能力を利用したりして不正咬合を解消する治療法です。小児の不正咬合では、筋機能療法単独で改善できることもあります。
筋機能異常に原因のある不正咬合の治療だけでなく、矯正治療後の咬合関係の安定を図るためにも行われます。
唇舌側弧線装置
唇側弧線装置は、唇側弧線という直径0.9㎜ほどの金属線と顎間ゴムで構成される矯正装置です。顎間ゴムの作用で、主線である金属線を遠心に滑走させることで、前歯部の舌側移動を行います。上顎前突症や反対咬合の治療に用いられます。
舌側弧線装置は、第一大臼歯に装着したバンド、設けられた維持装置、0.9㎜ほどの金属線で構成される矯正装置です。金属線に補助弾線などを付加し、この作用で混合歯列期の少数歯の唇側移動や乳歯の歯冠崩壊や早期喪失に対する保隙などに用いられます。
説得療法
説得療法は、歯科医師が不良習癖の悪影響を説明し、本人の意思によりその解消を試み、不正咬合の改善を図る治療法です。本人の理解と協力が必須なので、乳幼児には適用できません。
説得療法は、歯科医師の説明に理解を示せるおおよそ4〜5歳以降に有効な治療法とされます。
習癖防止装置
習癖防止装置は、説得療法では改善できない不良習癖を解消させるための矯正装置です。取り外しできない固定式と、取り外しできる可撤式に分けられます。
固定式の代表例は、舌側弧線装置にスパーを付与し、舌圧の遮断を図るタングクリブです。主に空隙歯列や開咬の改善に用いられます。
可撤式の代表は、吸指癖、いわゆる指しゃぶりの改善を目的として指に装着するフィンガーキャップです。
フィンガーキャップをつけると、キャップと指の隙間から空気が漏れるため、陰圧が得られなくなり、指を吸う感覚がなくなります。
なお、習癖防止装置自体には、歯を移動させる作用はありません。
拡大装置
拡大装置は、歯に接着する固定式拡大装置と取り外し可能な可撤式拡大装置に分けられます。
固定式拡大装置は上顎骨の正中口蓋縫合という、上顎骨の中央部の縫合部位を離開することで、間隙の骨化を図り、上顎骨を側方に短期間で拡大します。適応年齢は10〜18歳頃です。
可撤式拡大装置は、歯を頬側に傾斜移動させることで、歯列を側方に数か月以上かけて拡大させます。
顎外矯正装置
顎外矯正装置は、口腔外に装着する矯正装置の総称です。ヘッドギア、チンキャップ、フェイス・ボウなどさまざまなタイプがあり、不正咬合の症状に応じて使い分けられます。
一般的に、成長発育段階の不正咬合の治療に対して用いられます。
機能的矯正装置
機能的矯正装置とは、口腔周囲筋などの軟組織の機能的な働きを矯正装置として利用する矯正装置です。機能的矯正装置自体には、矯正力が生じません。顎骨の形態的変化や歯の移動により、不正咬合の改善を図ります。
種々ある機能的矯正装置の中でも代表的なものがアクチバトールという矯正装置で、下顎後退を伴う上顎前突症や過蓋咬合、機能性の反対咬合の治療などに用いられます。
床矯正装置
床矯正装置はレジン床と金属線で構成される可撤式の矯正装置で、混合歯列期を対象としています。
小児の過蓋咬合に適応される咬合挙上板や、小児の下顎遠心咬合に用いられる咬合斜面板が代表的です。
不正咬合のよくある質問
原則的に不正咬合の治療は自費診療です。
ただし、顎変形症などごく一部の不正咬合に限って、保険診療での治療が認められています。当てはまるかどうかは、主治医の歯科医師にご相談ください。
不正咬合の原因のひとつである不良習癖の解消は、成人期より小児期が容易です。
不良習癖を解消しないことには、歯列を整えても後戻りのリスクが避けられません。大人になってからでも治療できますが、小児期の方が治しやすいのでおすすめです。
マウスピース矯正なら目立ちません。またマルチブラケット矯正でも、歯の裏側に矯正装置をつけるタイプなど目立ちにくい治療法が開発されています。
ただ、歯並びの状態によっては適応できない場合がありますので、矯正歯科にて精密検査を受けることをおすすめいたします。
大人の方の場合、一般的に2〜3年程度です。
ただし、顎矯正手術が必要な方は、手術前の矯正治療だけでなく、手術後の矯正治療も必要になりますので、治療期間は5年程度かかることもあります。
顎の大きさと歯の大きさのバランスが取れていなくて、歯の大きさの方が大きい場合は、抜歯が選択されることが多いです。
ただし、バランスの差があまり大きくない場合は、歯を少し削って小さくしたり、インプラント矯正で大臼歯を後ろに動かしたりして、スペースを確保することもあります。